こんにちは!向上 条です。
「この不良、なんとかしといて」
「再発防止策を立てて報告して」
──そう言われても、なかなか良い対策が思いつかない…。
💬「とりあえず対策を書いたけど、これで本当に再発しないのか不安…」
💬「上司に“これじゃ不十分だ”って突き返された…」
💬「対策案を出したけど、現場での運用が無理すぎて、続かない…」
こういった悩み、現場では本当によくあると思います。
特にQC活動や不良対策に関わるようになると、**「形だけじゃなく、本当に効果のある対策を出せ」**と求められることが増えてきます。
でも大丈夫!
この記事では、そんな不安を抱えるあなたのために
✅ 再発防止策とはそもそも何か?
✅ 実際に使えるステップと考え方
✅ よくあるNG例とその回避法
✅ 顧客や上司が納得する「効果的な対策」の伝え方
を、わかりやすく解説します。
品質に関わる人なら絶対に知っておきたい再発防止の基本。
「これならいける!」と自信を持って提出できる対策を、いっしょに考えていきましょう!
\関連記事で一気に理解を深める!/
📦なぜなぜ分析のやり方|製造業の事例と初心者が失敗しないコツ📦なぜなぜ分析の失敗事例5選|うまくいかない原因と解決のコツ【チェックリスト付き】
✅ 再発防止策とは?基本の考え方を押さえよう
再発防止策とは、**「同じミスや不良を繰り返さないための“根本的な対策”」**のことです。
「とりあえず確認します」「気を付けます」といった表面的な対策では、またすぐに同じ問題が発生してしまいます。
そこで重要なのが、“再発しない仕組みをつくる”こと。
🔧 再発防止策=原因を物理的に潰す
たとえば、こんな対策が「物理的に再発しない」再発防止策です。
- 部品の向きを間違えないように、治具を変更する
- 抜け防止のため、センサーを取り付ける
- 入力ミスが起きないように、チェックシートの形式を変更する
こうした“物理的にミスが起きにくくなる工夫”が、最も効果的な再発防止策です。
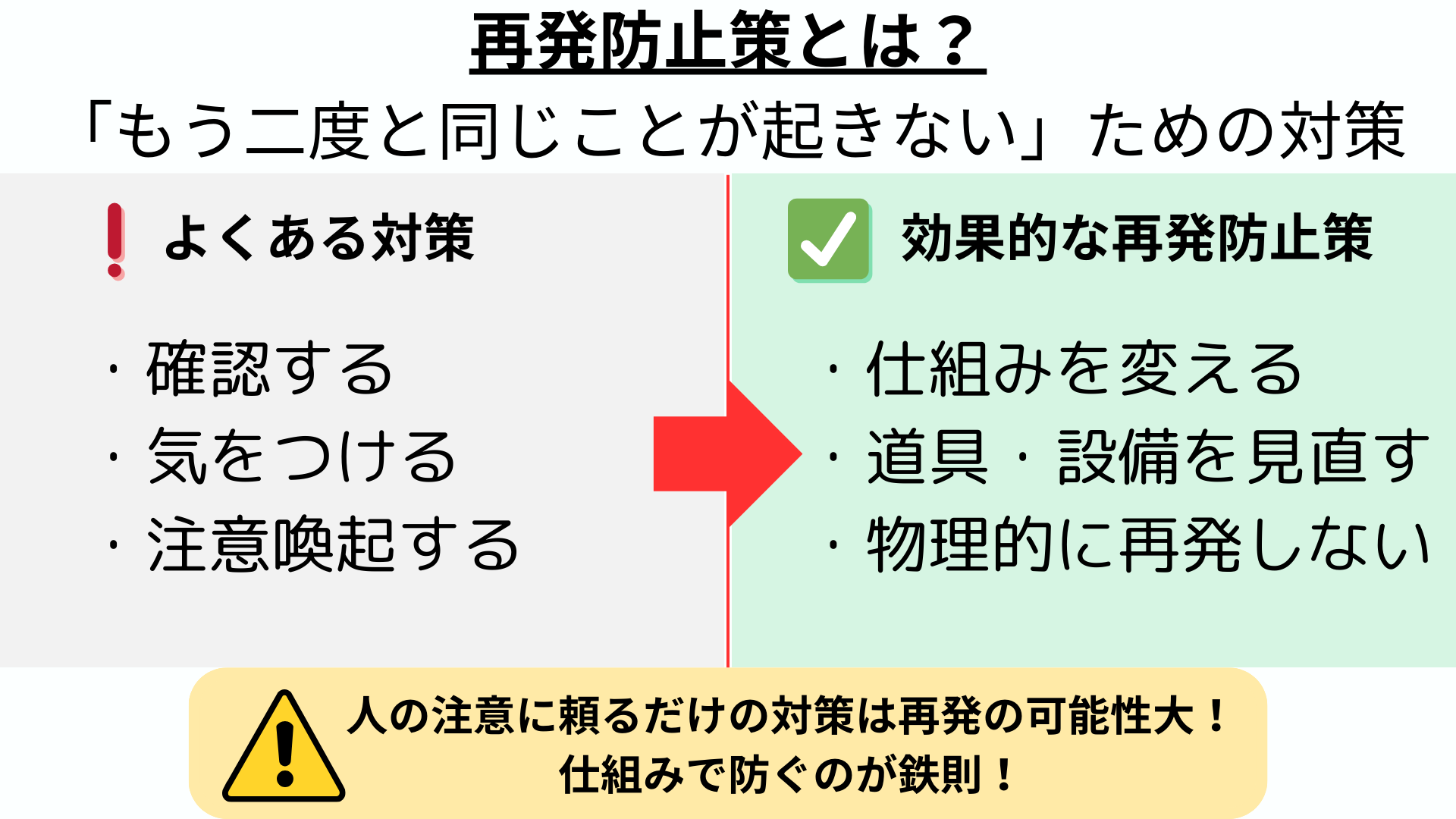
📌 実行可能な対策を立てることも重要
現場によっては、すぐに完璧な対策を導入するのが難しいケースもあります。
そんな時は、まずは現実的に実行できる方法を選び、段階的に改善していくことがポイントです。
- すぐに設備変更ができなければ、一時的に2人確認を導入する
- 対策を形だけで終わらせず、現場メンバー全員に内容を共有・理解してもらい、実際に運用できるようにする
無理なく続けられる形にすることが、持続可能な改善への第一歩です。
📢 再発防止策は、提出するために考えるものではありません。
形式的な対策ではすぐに再発し、結果的に自分の首を絞めることになりかねません。
「どうすれば同じことが二度と起きないか」
それを真剣に考え、実効性のある、効果的な対策を立てることが本質です!
⚙️ 再発防止策の進め方|7つのステップで「効く対策」を!
再発防止策は、ただの思いつきや感覚ではなく、手順を踏んで考えることが大切です。
以下のステップを意識すれば、現場でも「これは効果的だ!」と思える対策が作れます。
① 現物を確認する(現場・現物・現実)
まずは現場に行き、実際のもの(現物)を確認するところからスタート。
- どんな作業環境だったか?
- どの手順で作業していたか?
- 実際のモノにどんな異常があったのか?
📌 現物を見ずに机上だけで対策を考えるのはNG!
現場を見ることで、思い込みや想像で判断するミスを防げます。
② 原因を洗い出す(4M視点で)
次に、なぜ問題が起きたのかを関係者で話し合って洗い出します。
ポイントは、**4M(Man・Machine・Material・Method)**を軸に漏れなくチェックすること!
| 要素 | チェックポイント |
|---|---|
| Man(人) | スキル・慣れ・思い込み・教育不足など |
| Machine(設備) | 故障・設定ミス・不具合など |
| Material(材料) | 不良品の混入・規格外の素材など |
| Method(方法) | 手順書の不備・確認漏れ・やり方の違いなど |
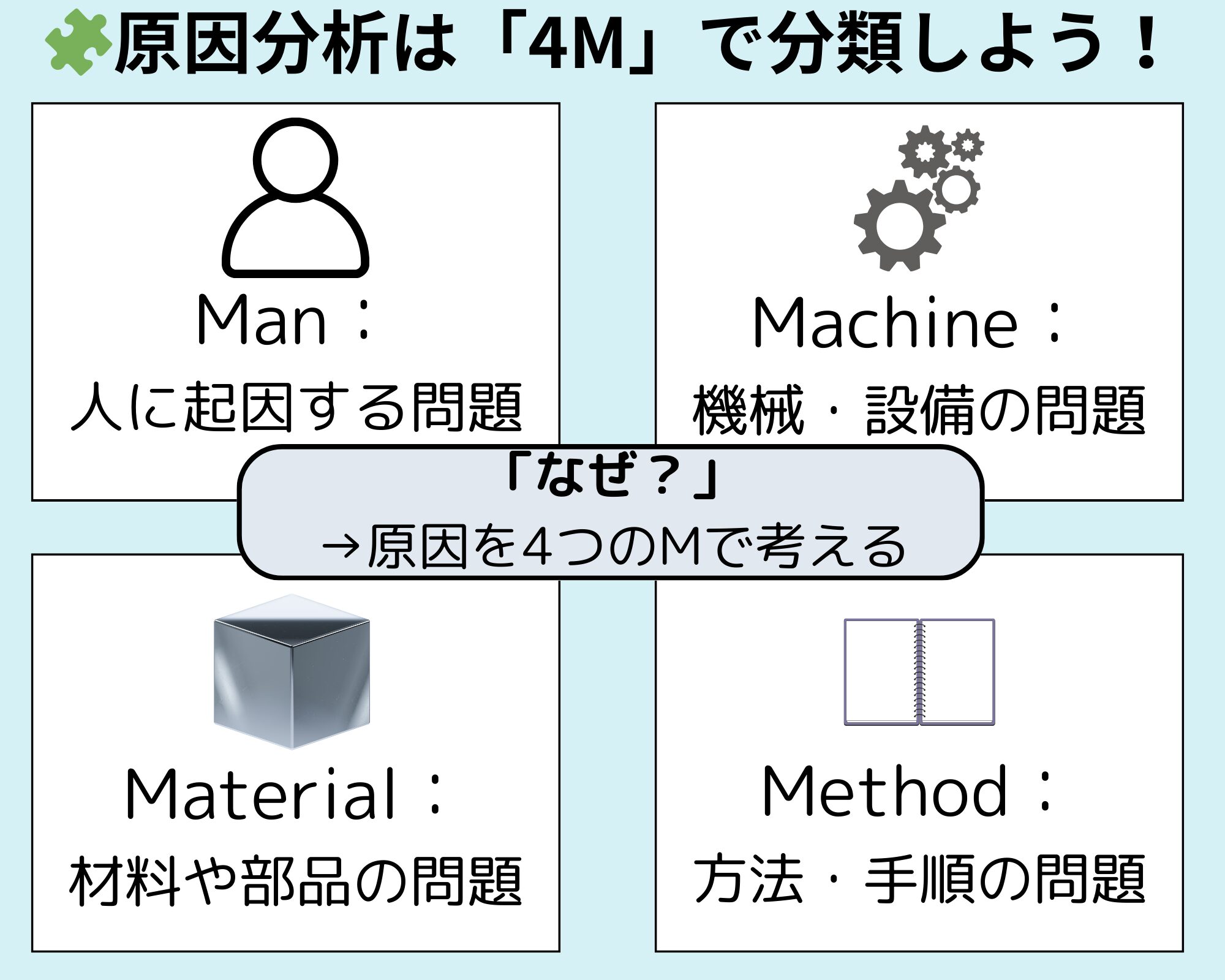
🔍 また、「初回不良」か「再発不良」かでも考え方が変わります。
特に再発不良の場合、なぜ以前の対策が機能しなかったのか? にも注目しましょう。
③ 対策の立案・実施
原因が明らかになったら、それを防ぐための**「再発しない対策」**を立てます。
重要なのは…
- 物理的に再発しない仕組みか?
- 作業者に依存しない仕組みか?
- 実行可能な内容か?
もしすぐに対応できない場合は、**暫定対策(例:チェック強化)と恒久対策(例:設備改善)**をセットで立てると効果的です。
④ 報告・承認
考えた対策は、上司や関係者に会議などで報告・説明し、合意を得るようにしましょう。
この段階で「もっといい方法は?」とフィードバックをもらえることもあります。
⑤ 標準化・横展開
良い対策ができたら、それを標準手順に落とし込みましょう。
- 作業手順書を更新
- 標準作業を見直し
- 他の類似工程にも展開(横展開)
📌 対策は“その場限り”にしないことが大切です!
⑥ 教育・訓練
新しい手順やルールは、作業者にしっかり教育・訓練することが重要です。
- 繰り返しミスをする人には個別のフォロー
- 教育記録や訓練履歴を残すと管理がしやすい!
⑦ 日常の管理・フォロー
せっかくの対策も、日々守られていなければ意味がありません。
- 実作業の確認
- 実施状況をチェック
- 良くできていればしっかり「褒める」ことも大事!
📌 管理者やリーダーの「見に行く」「声をかける」が継続の鍵!
⚠️ よくある間違い・失敗例|“対策を立てたのに再発”を防ぐには?
せっかく再発防止策を立てたのに…
「結局また同じ不良が起きた…」
ということ、ありませんか?
ここでは、ありがちな失敗パターンとその理由を紹介します!
❌ 1. 「もう気をつけるから大丈夫!」は一番あてにならない
不良が発生した直後は、
「もう二度とこんなこと起こさないようにします!」と強く思うものです。
でも、時間が経てばその記憶も意識も薄れてしまうのが人間です。
📌 “気をつける” “意識する”では再発は防げません。
根本的にミスを防ぐ仕組みをつくることが重要です。
❌ 2. 再発防止と是正処置を混同している
是正処置=一時的な応急対応
再発防止=二度と同じことが起きない仕組みづくり
たとえば…
- 是正処置:「検査員が見逃したので、再検査しました」
- 再発防止:「見逃しが起きないよう検査工程を2人でクロスチェックに変更した」
📌 顧客や上司が求めているのは再発しない仕組みです!
❌ 3. 推測で「なぜなぜ分析」している
「たぶん〇〇だったと思う」
「おそらく△△が原因かと…」
…このように、現場に行かず“なんとなく”で原因を決めてしまうのは非常に危険です。
そこで意識したいのが 三現主義(現場・現物・現実)。
📌 三現主義とは?
- 現場に行って
- 現物(実際の不良品や設備)を見て
- 現実(実際に何が起きたか)を把握する
この3つを徹底することで、事実にもとづく正確な原因特定が可能になります。
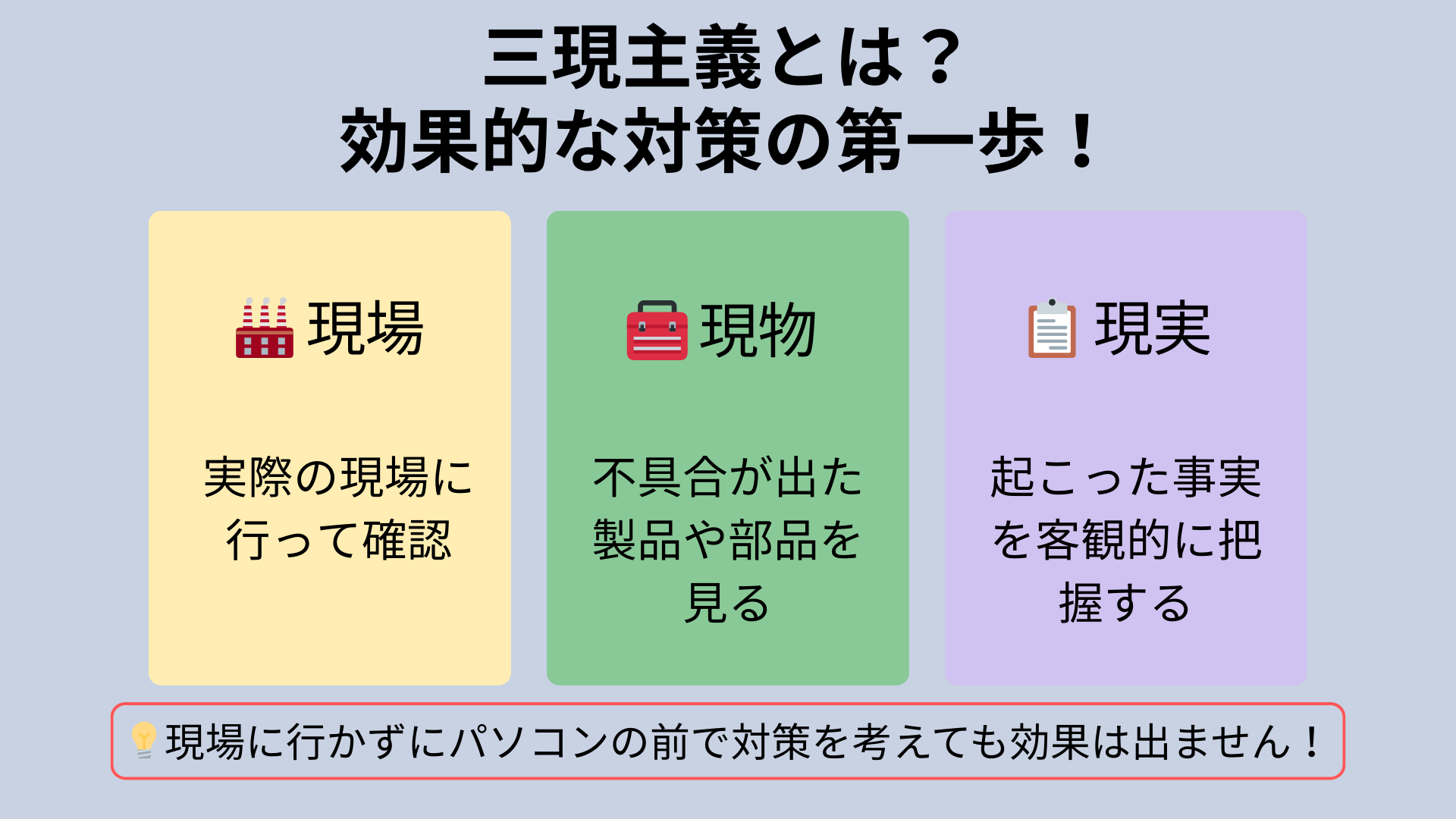
再発防止策は「真の原因」に対するものでなければ効果がありません!
机上の空論にならないよう、まずは現場をしっかり確認しましょう。
❌ 4. 対策が「継続できない」「実行できない」
- その場では良さそうに見えるけど、現実的に無理な対策
- 曖昧で、結局誰も実行しない
- 一度やって満足して継続されない
📌 対策には「実行可能性」「継続性」が欠かせません。
理想論ではなく、実際に“やれる・続けられる”対策を選びましょう。
✅ 上手に再発防止策を進めるための“5つの着眼点”
再発防止策を立てたはずなのに、
「結局また同じ不良が出た…」
そんなこと、ありませんか?
それは、“原因は分かっていたけど、対策の詰めが甘かった”ケースが多いです。
ここでは、実行フェーズで注意すべき具体ポイントを整理しておきましょう。
1. 再発防止策は「実行されてこそ意味がある」
どれだけ完璧な計画でも、やらなければゼロ。
現場が無理なく動けるレベルになっているかを確認しましょう。
2. 今日の不良は今日のうちに対応する
時間が経つほど記憶は曖昧になります。
現場の状況、作業環境、作業者の記憶…
“新鮮なうちに”原因を探って“早めに”手を打つことが、再発を防ぐ最大のポイントです。
3. 全員が「本当に必要な対策」だと納得しているか
関係者の“腹落ち”がないままスタートすると、
「やらされ感」で続かない or 手を抜かれることも…。
対策の背景や目的を共有するミーティングを挟むのが効果的です。
4. 本質は「見張ること」ではなく「仕組みを変えること」
前セクションで述べたように、
✅ チェック項目を増やす
✅ 確認作業を増やす
…だけでは不十分。
この章では、「本当に仕組みを変えるには?」に注目しましょう。
5. 対策は“続く”ことが大前提
その日限りの気合や注意喚起では、1ヶ月後に消えてしまいます。
継続性を担保する方法:
- 点検・記録などを「業務フローに組み込む」
- 教育・訓練を定期化
- 振り返りタイミングを設定(例:月初に再発チェック)
🗣 上司や顧客に“納得される”再発防止策の書き方
「この対策、本当に効くの?」「また同じことが起きるんじゃないの?」
そんな上司や顧客からの不安の声を、“一文”で払拭できる表現があります。
✅ キーワードは「〇〇したら××が起きる状態にした」
たとえば──
📌 「逆向きにセットしようとすると、金型が閉じないようにしました」
📌 「手順を忘れると機械がスタートしない設計にしました」
📌 「同じ間違いが起きた場合は、アラームが鳴ってラインが止まるようにしました」
このように、「動作・行動に対して、必ず“仕組み”が働く」ことが伝わる表現にすると、
「お、それは再発しなさそうだな!」と納得感が一気に高まります。
⚠ 「~しないように注意します」はNG!
逆に、
❌「確認を強化しました」
❌「今後は気を付けるように周知しました」
…といった“気持ち・行動ベース”の対策は、信頼性に欠けます。
大事なのは、「人の意識」に頼らずに防ぐ仕組み。
“仕組みで止める or 防ぐ”という考え方が、再発防止の基本です。
📌 「~が起きたら~になるようにした」
このテンプレを意識するだけで、報告書や報告会での説得力が大きく変わります!
🧭 再発ゼロを目指すあなたにおすすめの記事
✅ まとめ|再発防止策の基本は「仕組み」で防ぐこと!
不良をゼロにするのは難しくても、**「同じ不良を繰り返さない」**ことは可能です。
その鍵となるのが、再発防止策の考え方。
もう一度、ポイントを振り返りましょう。
🔧 再発防止策の基本
- 原因と対策はセット!
- 根本的な原因を見極める
- 「確認する」「気をつける」で終わらせない
- 物理的に再発しない仕組み化を目指す
- 続けられる内容にする
📌 実行しやすく、伝わりやすい一文に!
「〇〇したら××が起きるようにした」
→ これだけで、上司や顧客への説得力が格段にUPします!
🛠 改善の鉄則
- 今日出た不良は、今日対策を始める
- 三現主義(現場・現物・現実)を大切に
- 対策を立てて終わりではなく、継続と確認がカギ!
🎯 再発防止は、自分の未来を守ること!
対策は形式的な報告ではなく、“未来の自分や仲間を守るためのアクション”です。
「やっておいてよかった」と思えるような改善に、ぜひ取り組んでいきましょう!
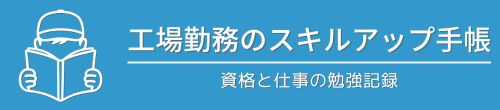
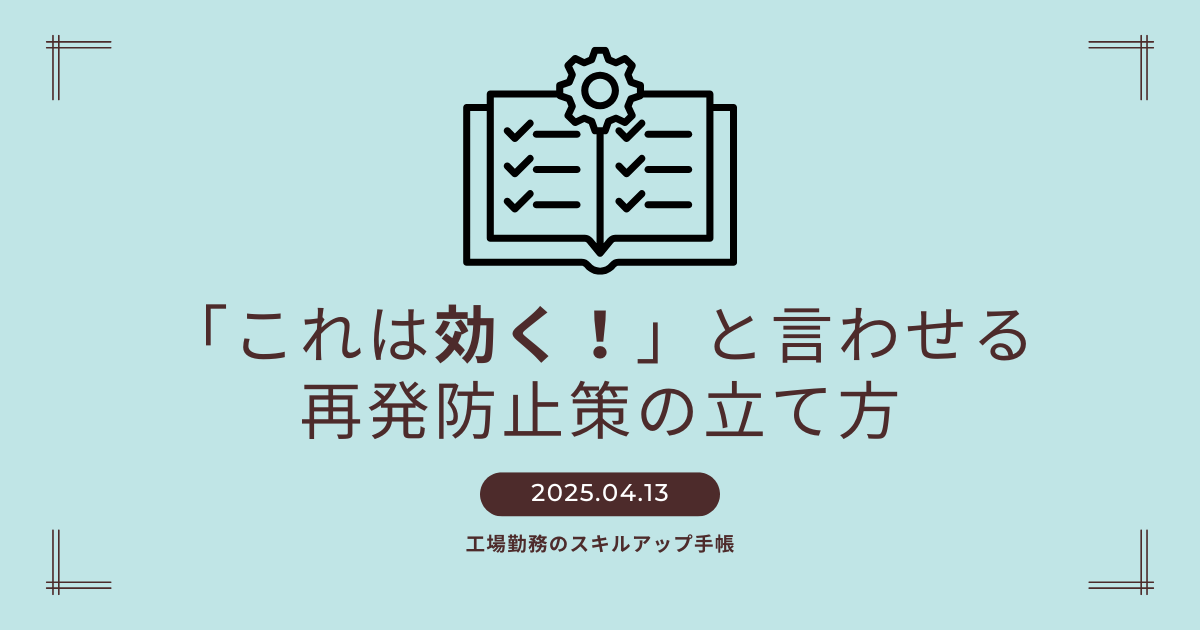

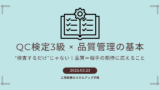



コメント